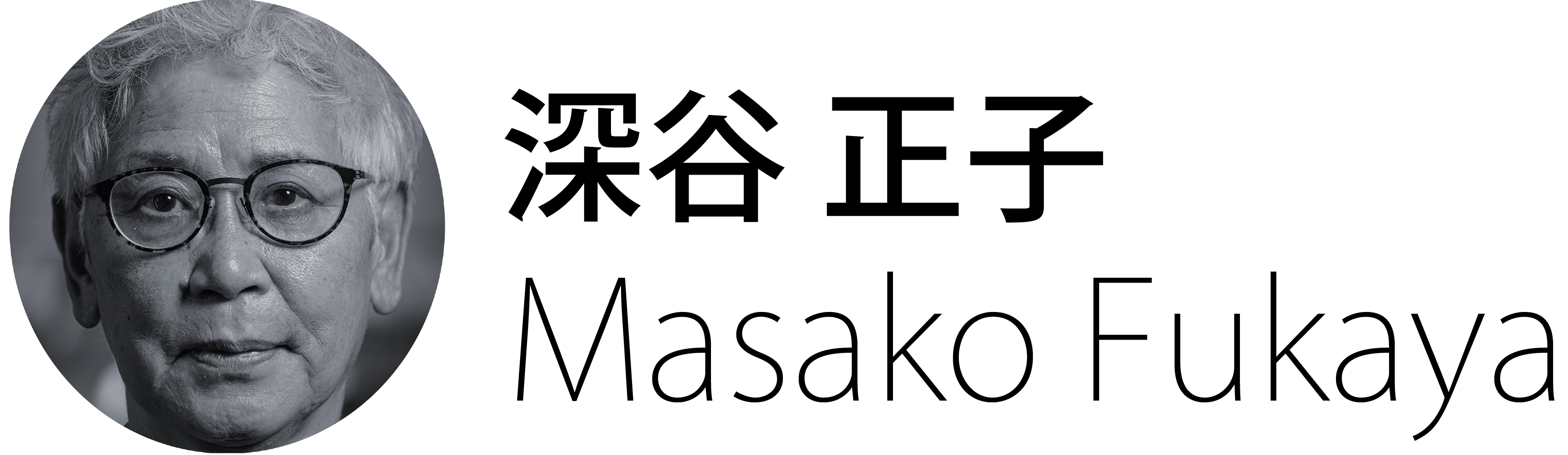肉でも皮でもなく、骨
目の前に人物がいるだけで、動きやシチュエーションなど直感的に事が進行する
<個の認識から他者への関係へ>
感情は他者の認識、関わりから生まれる。自己の外部をどう捕らえるか。刺激にどう反応するのか。関係、構造や組織のズレ、ゆがみなど抱えるものは途方もなく拡がり始める。多くの物語はここにこそある。私の作品の多くは、個の内部の問題を主に創ってきたが、関係性などのテーマは観る人の推測に委ねてきた。人が本来持っている暗黒の部分は否定してもチャンスを狙い神出鬼没に、誰にでも現れては消える。それらの葛藤にこそ心躍る物語が存在するであろう。関係性の問題は、私の作品の中では欠落していると思う。この課題は笑いながら小脇に抱えていきたい。
ーダンスワーク70 2015夏号よりー
深谷正子ソロ公演「棘を呑む」
2018年12月26日(水)19:00 六本木・俳優座劇場
<深谷正子の特質>
長谷川六
深谷正子は、2012年TOKYO SCENEにノミネートされた公演以降、劇場公演をしない。
劇場とはプロセニアムがあり固定椅子だと仮に定義するとして、深谷は観客との距離の近い空間を選ぶ。それは毎月のように、呼吸をするようにパフォーマンスしたいという、強い欲望、それはいま言わなくてはならないこと、いましなくてはならないという強い危機感からだと推測する。深谷の作品から感じるクライシス(crisis危機)、それを伝達したいという強い意志を感じる。そのために平和な時間を排除する空間の異化をおこなう。それが装置、衣装、小道具などに転嫁されて凹凸やつぶれたトマトを身体から落とすというエキセントリック(eccentric異常な)風景となって顕われる。
劇場文化と決別するという宣言などは問題外で、それもこれも含めてパフォーマンスできるところであれば、どこにでも行く、どこでも行う、要請があればさまざまなパフォーマンスシーンに登場する、この開放的なスタンスは、深谷が1976年に最初の上演をして以来、長い時間をかけて醸成したものと推測できる。そして自らの身体を犠牲体のように差出し晒すことで、自らの疑問を解き放ちこの時代に限りなく生み出される疑惑やクライシスに立ち向かってゆこうとする。これは、深谷正子の特質であり、また舞踊の本質であろう。行為から生じる作品はデーターとなり、それを生み出しているものが何か、また誰かということが屹立(キリツ)する。それが深谷だ。ダンスワーク60(2011春号)に寄稿した深谷は、「ダンスをつくる原体験」を列挙している。そこには日常的な作業が記載されているが、その気づきと実行こそ現代人に求められる振幅の広さで、深谷正子の魅力なのではないだろうか。
わたしは、言語で、深谷正子の仕事を記録し語り、自分が得た感覚を伝えようと格闘したが、それがいかに脆弱なものか、書き進むために読み返して感じている。身体パフォーマンスから得られ感じることから、作者の真実を理解することは実に困難である。しかし、パフォーマンスされるその場にいなくてはならない。それは、あらゆる規範から解き放たれた自由な瞬間であるからで、同じ空気を呼吸することで伝わる意識を受けるからではないだろうか。
<今回の劇場での公演についてインタビューしてみた>
深谷正子
(1)動体証明について
自分がこれまで獲得してきた身体表現は、観客と踊り手との距離が近いオープンスペースで成立すると思って活動してきたわけだけれども、今では、客席と舞台で成立する劇場でも成立するんじゃないかと思うようになってきた。自分自身の中には、その根拠を掴んでいるわけだけれども、これまでそれを証明していない。証明(アウトプット)したい、そういうチャンスだと思っている。
(2)長谷川六さんに関して
六さんは、2001年からのダンスの犬以前って、実はあんまり評価してくれていない。私が余分なものを捨てて表現するようになって、面白いねって六さんは評価してくれるようになった。それが、ダンスの犬。この18年活動を続けてきて、要るもの・要らないものの仕分けができてきた、そう思えるし、その手応えもある。今であれば、舞台でやっても六さんが面白いと思えるところまでもっていけるんじゃないかなと思っている。まぁ、やってみないと分からないけれども。
(3)表現の創作・クリエーションについて
今までのオープンスペースや小スペースと違って舞台での表現。舞台でどう成立させるか今までにない新しい身体の表現(舞台を意識した表現)を色々やってはみるんだけど、やっぱりできないものはできないのよね。結果、必要ないなって思える。いわゆる外連味(ケレンミ)だなぁって。結局、いつもどおり自分で確認してきた身体に染み着いてきた表現方法でいいんだなぁっていうのを改めて実感しながら、作業している。
(4)照明:斉藤香
俳優座での公演の話を頂いた時、そういう場(劇場)とは決別したっていう今までの思いもあったから、やるつもりもないと一度はお断りを。でも、子供たちのダンス教室の発表会の照明担当に斉藤香さんが来て、この人の明かりで舞台でやりたいって思ったの。彼女との出会いは理由の一つとして大きい。
彼女の明かりは、情緒に走らない。時間と空間の捉え方がね。彼女の力を借りて、どうプラスアルファがあるか、私自身もそれを見てみたい。
例えば、悲しい時のシーンをつくる明かりってあるじゃない?あざとくそれを表現するのが舞台芸術の在り方みたいなところはあるけど、彼女の明かりはそうじゃない。彼女の明かりは、光と影の扱いが非常に上手い。若い身体をもっとクリアに映し出すとか、年取った身体を表すとか、そういう時間経過がどう流れていくのかを現象として陰と陽の明かりづくりをしていく人。
私の動体証明は、前面に情緒を押し出すことではなく、情緒が発生する時っていうのは、最後の最後。私が出した肉体の結果と受け手・観客との何かが結合した時、合致した時に成立する。情緒は具象として最後に受け手に伝わるんだろうと考えている。それを先取りして投げかけようというスタンスではない。彼女の明かりもそう。
だから、彼女と舞台をどうつくれるか楽しみにしている。